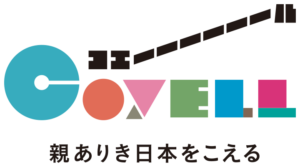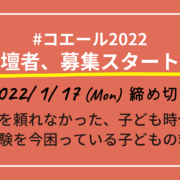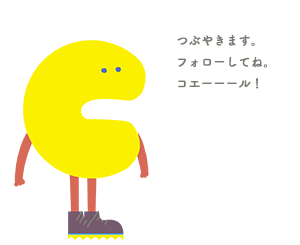「生きづらいのは、なぜ?」。その理由について考える「ダイバーシティ&インクルージョンセミナー」(全2回)が6月1日夜、オンラインで始まりました。
「コエール2022」と連動するプログラムとして、ブリッジフォースマイル(B4S)のインターンシップに参加する大学生が発案。さまざまな社会問題の当事者や、企業のCSR(企業の社会的責任)担当者を招き、「一人一人が生きやすい社会」の実現に向けて何ができるのか、「ダイバーシティ(多様性)」と「インクルージョン(包括)」をキーワードに、参加したみなさんと一緒に考えるのが狙いです。
第1回は、ミノンさん(LGBTQ)、滝澤ジェロムさん(児童養護施設出身者・元無国籍児)、川向緑さん(日本オラクル株式会社コーポレート・シチズンシップJAPACシニアマネージャー)の3人が登壇しました。
■いろんな「生きづらさ」 職場で気付く
ミノンさんは、中高生のころ、自分がゲイだと気付きました。社会人になって初めてゲイの友達ができるまで、ずっと自分は「人とは違うから」と思って生きてきたといいます。恋の悩みや性、将来について話せる友達ができ、「遅れた青春がやってきた」と感じたそう。精神的に安定し、居場所ができたと実感するようになってからは、それまで悩まされてきたアトピー性皮膚炎なども落ち着き、体調面も快復しました。
一方、社会人になって、ある発見がありました。自分だけが特別な存在で、生きづらいと感じていた職場内で、「女性もマイノリティだ」と気付きます。さらに「子どものいない人」「結婚をしていない人」も違う扱いをされ、「何か、自分らしさを出せていない」「それって自分と似ている」「生きづらいんじゃないかな」と感じたそうです。
現在は、自分が選んだ居場所で得た仲間やコミュニティを、家族と同じくらい大事だと考え、この先、人生を共にできる仲間と出会えて良かったと思っています。
ここ10年で、性的マイノリティへの関心が高まり、若い世代が安心してカミングアウト(セクシャリティの告白)ができる環境になり、「すごい進歩!」と感じる一方、同性婚が認められていなかったり、LGBTQを揶揄する場面をテレビやメディアで見ることもあったりし、「日陰の身」と感じて、職場や家族でカミングアウトできない当事者も少なくないといいます。年輩の人がどんな老後を迎えているのか、海外の情報はSNSなどで接することができるものの、国内ではまだ、直に会って話を聴く機会がないと感じています。
また、同性婚を望まない当事者もいるなど、「当事者」でもみんなが同じ意見ではないことについても、理解してほしいと話しました。
■「ここに存在しているよ」
滝沢さんは、小学4年生から高校卒業まで児童養護施設で暮らしました。この春から東京都内の児童養護施設で働き始め、自立支援などを担当しています。無国籍だったこともあり、「子どもの権利」をテーマに、大学や企業で講演活動も行っています。
ご両親がオーバーステイ(不法滞在)で、本来は滝澤さんが生まれた時、フィリピンに出生届を出さないと国籍を得られなかったのに、そのことをよく理解していなかったため、生まれて22年間、「無国籍」状態で育ちました。
無国籍だと知ったのは、中学2年生の時。施設職員は入所時、「フィリピン国籍」と報告を受けていたといいます。そして、多くの困難に直面します。
医療費は「10割負担」。児童養護施設に入っていた間は「無料」でしたが、18歳で退所後は「10割負担」となり、病院に行けなかったそうです。就労では、アルバイトもできず、奨学金も対象外に。移動も制限され、住んでいる都道府県から出ることが許されず、修学旅行や友人と遠出することもできませんでした。20歳で在留資格を得て、一部緩和されましたが、「自分に根っこがない感覚」は続きました。
さまざまな手続きを経て、今年4月に出生届を提出し、フィリピン国籍を取得することができました。国籍を取った今、フィリピンに行ってみたいそうで、さらに次の目標は、日本国籍を取得することだそうです。
「ダイバーシティ」と「インクルージョン」について、「〝ここに存在しているよ〟〝本人の意思や権利が保障されること〟を守ることが、ダイバーシティやインクルージョンにつながるのではないか。そういう社会になっていったらいいな」と望みました。
■「〝社会モデル〟のめがねをかけて見て」
川向さんは、外資系IT企業で、CSR(企業の社会的責任)などを担当しています。なぜ、企業がD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進するのか。そんな問いかけから、話を始めました。
一つは「競争力のため」、もう一つは「心理的な安心感のため」と説明。競争力については「多様な人材が多様な視点で働くことが、イノベーションを生み出す。企業が生き残っていくためには、多様性、D&Iが必要だ」と、心理的な安心感については「その人本来の、自分自身に対して100%嘘偽りのなく生きたり働いたりできる環境が、その人の能力を最大限引き出し、安心感につながる」と解説しました。
D&Iは、もともと人権を守るための考え方として出発しましたが、その後、企業が経営改善や組織改革に向けて経営陣や株主を説得するため、「競争力のため」「心理的な安心感のため」という文脈で説明するようになりました。
アフリカ系アメリカ人に対する警察の残虐行為などを引き金に始まった人種差別抗議運動「ブラック・ライブズ・マター(Black Lives Matter、BLM)」を機に、再び「基本的人権」の守るための考え方として再認識されるようになってきたと感じるそうです。
川向さんは、車いすの人が駅の階段の前で上れずに困っている場面を例に、そこにある「困難」の原因について、「その人が車いすに乗っているから」と見るか、「階段があるから」と考えるか、で二つに分かれると説明。前者は個人の心身機能が原因とする「個人(医学)モデル」、後者は社会のつくりや仕組みに原因があるとする「社会モデル」に分類されると解説しました。
さらに「社会は〝マジョリティ〟〝特権〟のある側の仕様に合わせてつくられているケースがほとんど。マジョリティの側にいると、マジョリティ仕様につくられていることにすら、無自覚に出あることが多い」と指摘。社会に横たわる〝困難〟を透明な「自動ドア」に例えた上智大学の出口真紀子教授(文化心理学)の話を紹介しながら、「マジョリティや特権を持つ人は、自然に自動ドアが開き、(困難を)意識せずに進める。けれども、マイノリティや抑圧される側の人が通ろうとしても、その自動ドアは開かず、透明な困難の壁が立ちはだかる」と説明しました。
その上で、インクルージョン研究家の野口晃菜さんの言葉をひき、「特権がある人こそ、社会モデルのめがねをかけてみる」ことが大切だと訴えました。
さらに、「平等・公平」や、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」が掲げる「だれひとり取り残さない」という考え方などについても解説しました。

ミノンさん、滝澤ジェロムさん、川向緑さん
■クロストーク
クロストークでは、登壇した3人の方が、それぞれの感想を交え、語り合いました。
ミノンさんは、昨年、ご両親にゲイだとカミングアウトした際のことを紹介。母親に「いつから、そう思っていたの」と聞かれ、「中学生のころ」と答えたところ、「そんな前からなんだ。私、たぶん、いろいろ無神経なことを言っちゃたけど、気付いてあげられなくて、ごめんね」と言われたそうです。「ああ、そう思ってくれる親だったんだ。もっと早く言えばよかった。すごく、うれしかったですね」と振り返りました。
滝沢さんは、高校生の時、彼女に、国籍も在留資格もなく、日本に住む権利がないと伝えたところ、「そうなの」と言って泣き始めたそう。「背景事情が分からなくても、〝いつかいなくなってしまうんだね〟って。つらい人生を送っていたことに理解を示してくれた」という。社会人になって、給料1カ月分を渡してくれるなど、「なんとかしたい」という気持ちを行動に移してくれたことが、すごくうれしかったといいます。
川向さんは「〝当事者〟ってなんだろう」と問いかけました。「そこに違和感があって。ミノンさんの言っていた〝男らしさの生きづらさ〟っていうのも、男性としての当事者性ではないか。一人の中に、いろんな〝当事者性〟があるし、当事者じゃない人なんて、どこにもいない気がすます。だれもが、何らかの当事者性を持っている」と話しました。
「当事者」という言葉で、ひとくくりにされたり、「タグ付け」されたりすることに、抵抗感を持つ人も少なくありません。
当事者の抱える課題や困難さについて、世間一般で、知られてないゆえの「生きづらさ」がある一方、「取り上げて強調されたくない」と考える当事者もいます。
では、マイノリティ性について、どう話せばいいのか—。
ミノンさんは「最後にやっぱり、何か一つ薄い皮みたいなものがある。人を選んで話すかどうか決める」そうです。
滝澤さんは「話さない方がこのままの関係が続くだろうな、話したことによって逆に関係をぶち壊しにしてしまうこともあるな、と思うこともある」といいます。
川向さんは「マイノリティ性をカミングアウトすること。その人しか選べない権利」と指摘。ご自身が「乳がん」という当事者性を持つ経験を紹介しながら、「職場でフルオープンに話すと、隠して働いている人たちからコメントもらったり、中にはレッテル張りされたりすることもあるようだ。でも、オープンにした方が、以外と働きやすいかもしれない」と話しました。
次回(第2回)は、6月15日(水)20時〜21時30分、オンラインで開催。神原由香さん(アルビノ)、塚田友樹さん(視覚障がい者)、木幡美子さん(株式会社フジテレビジョンCSR・SDGs推進室部長)の3人が登壇します。