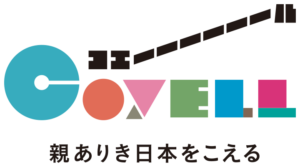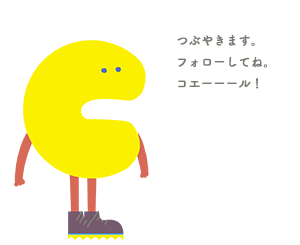2020年7月4日に親を頼れない若者によるスピーチイベントを行いました。
その一部を紹介し、社会的な背景とともに振り返ります。
まさや/20代/男性
僕はシングルマザーの母から虐待を受け、小学3年の時に児童養護施設に入りました。施設の生活は楽しかったけれど、進路を考える際には、18歳で退所して独りで生きていくことを前提にせざるを得ませんでした。僕は施設で育ったことを言い訳にしたくなかった。施設育ちだからいい仕事につけないとか、周りよりできないとかが嫌だったから、勉強はオール5を取るほど頑張り、高専に進学しました。別に工業をやりたかったわけではありません。就職に有利で大学編入も視野に入る、つまり失敗の危険性が少ないと思ったからです。高専でも頑張ってトップで卒業し、大学相当の資格が取れる専攻科に進みました。でも、いよいよ就職を考える時期になって、工業の世界でずっと生きていく自分を想像すると、死にたいほど苦しくなりました。決してやりたいわけではない、ただ生きるためだけに選んだ道でずっと過ごす意味はあるのか。悩んだ末に退学し、本当にやりたいことを探し始めました。
児童養護施設出身者の進路選択の幅は年々広がり、かつてはごく一部だった大学・専門学校への進学率は約3割まで増えました。奨学金や生活費支援などの制度が整ってきたためです。とはいえ、日本全体の進学率が7割を超えているのに比べれば、施設出身者の進学率はなお低水準です。また、施設出身者の場合、進学先の半分近くは専門学校で、「手っ取り早く手に職をつける」意識が強いことがうかがわれます。施設職員など周囲の大人が「安心・安全」な道、つまりとりあえず就職がしやすい道を勧めがちであることも影響しているようで、まさやの場合も、そうした雰囲気に押されたといいます。
ですが、とりあえず就職できれば安心とは言えません。ブリッジフォースマイルの調査では、施設を退所して就職した若者の離職率は約1年後で26%、3年後には45%にのぼります。キャリアが不十分なまま離職し、しかも頼れる親のいない彼らがより条件の良い仕事に転職するのは困難です。だとすれば、彼らを支える大人がやるべきことは、目の前の安心・安全にとらわれず、自分のやりたいことをじっくり考えさせ、自ら選ぶ力を身につけさせることではないでしょうか。本当にやりたいことがあれば、多少のリスクがあっても挑戦してみる。あるいは、とりあえず大学などに入ってじっくりと将来を考える。一見回り道であっても、自分で考え、選んでいくことが、充実した人生のためには必要なはずです。
僕は言い訳をしたくないと言いつつ、一番大事なところでしていたのかもしれません。親がいないことを言い訳に目の前の安心だけを求めていました。親がいないことを言い訳にしてしまうのは簡単です。でも今施設にいる子どもたち、彼らにかかわる大人たちには、進路選択についてもう一度考えてみてほしいのです。僕が中学生の時に比べ、進学にかかわる制度はさらに充実してきています。もっとやりたいことがやれるようになっている。言い訳なんてもったいない。ほんの少し早く自立した先輩からのアドバイスです。
執筆 : 原沢 政恵