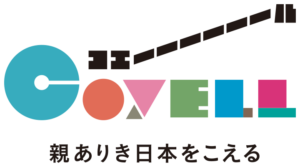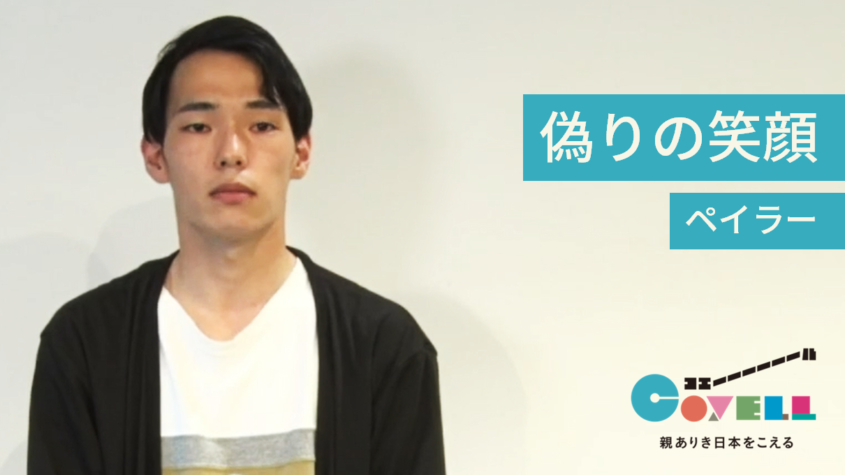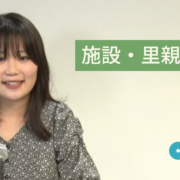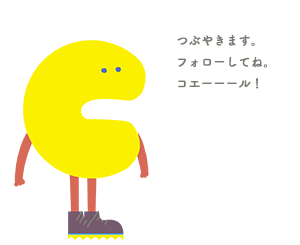2021年7月3日(土)に親を頼れない若者によるスピーチイベントを行いました。その一部を紹介し、社会的な背景とともに振り返ります。
ペイラー/20代/男性
児童養護施設で育った私は、一般の方が思い描く「当たり前」とは違う生活をしてきました。そんな私には、何気ない質問がどう返答すべきかわからない難問となることがあります。たとえば、高校生の時に言われた「いまどきスマホ持ってないとかおかしくね?」。施設ではスマホを持つには条件があり、私はそれをクリアしていなかったのです。社会に出てからよく聞かれるのは、「今って実家暮らし?」。これも毎回返答に困ります。本当のこと、つまり施設出身であることを伝えると、必ずといっていいほど場が凍るからです。だから、「親と仲良くないので一人暮らしです」などと笑顔で嘘をつきます。
また、施設出身であることを話すと、返ってくる言葉があります。「親と生活できてないとかかわいそう」「つらい生活を送っているんだね」と心配されてしまうのです。自分で決めた道です。勝手にかわいそうと決めつけないでいただきたい。
こうした経験を経て、困った時は偽りと笑顔でごまかすのが一番平和と思うようになりました。でも、そうすると周りの人は「あの人はしっかりしているから大丈夫」と思ってしまうようです。まったくもって大丈夫ではなくても、です。
児童養護施設で暮らした子どもは、原則として18歳で施設を退所します。里親のもとで暮らした子どもを含めると、年間2000人ほどが、社会的養護のもとから社会に巣立っています。親に頼れない子どもが自立して生きていくにはさまざまな困難がつきまといますが、そのひとつが、自分の境遇を人に語ることの難しさです。
私たちの社会では長い間、「両親と子ども」が当たり前の家族の形とされてきました。離婚が増えた近年は、片親家族も徐々に当たり前になってきましたが、「親がいない・いても頼れない」子どもたちの存在はまだあまり知られておらず、聞かされた人はとまどい、対応がぎくしゃくしてしまうことが多いようです。
家族の形は多様化しています。親のもとで暮らすことが適切でなければ、施設や里親など社会的養護のもとで暮らすのは当たり前のことなのです。今後は、同性婚家族などさらに新しい形の家族も増えていくでしょう。さまざまな家族の形を人々が自然に受け入れることで、この社会はもっと暮らしやすくなるはずです。
考えてみてください。自分が思う当たり前は本当に当たり前なのか? 隣の人の笑顔は本物か? 実は助けを必要としているのではないか? 助けを必要としていそうな人がいたら、一緒にご飯を食べてください。そして、「困っていることはない?」とさりげなく聞いてみてください。「何かあったらいつでも相談しろよ」と声をかけてください。困っていることを話してくれたら、しっかり聞いてあげてください。それで救われる人はいる。私はそう思っています。
執筆 : 原沢 政恵